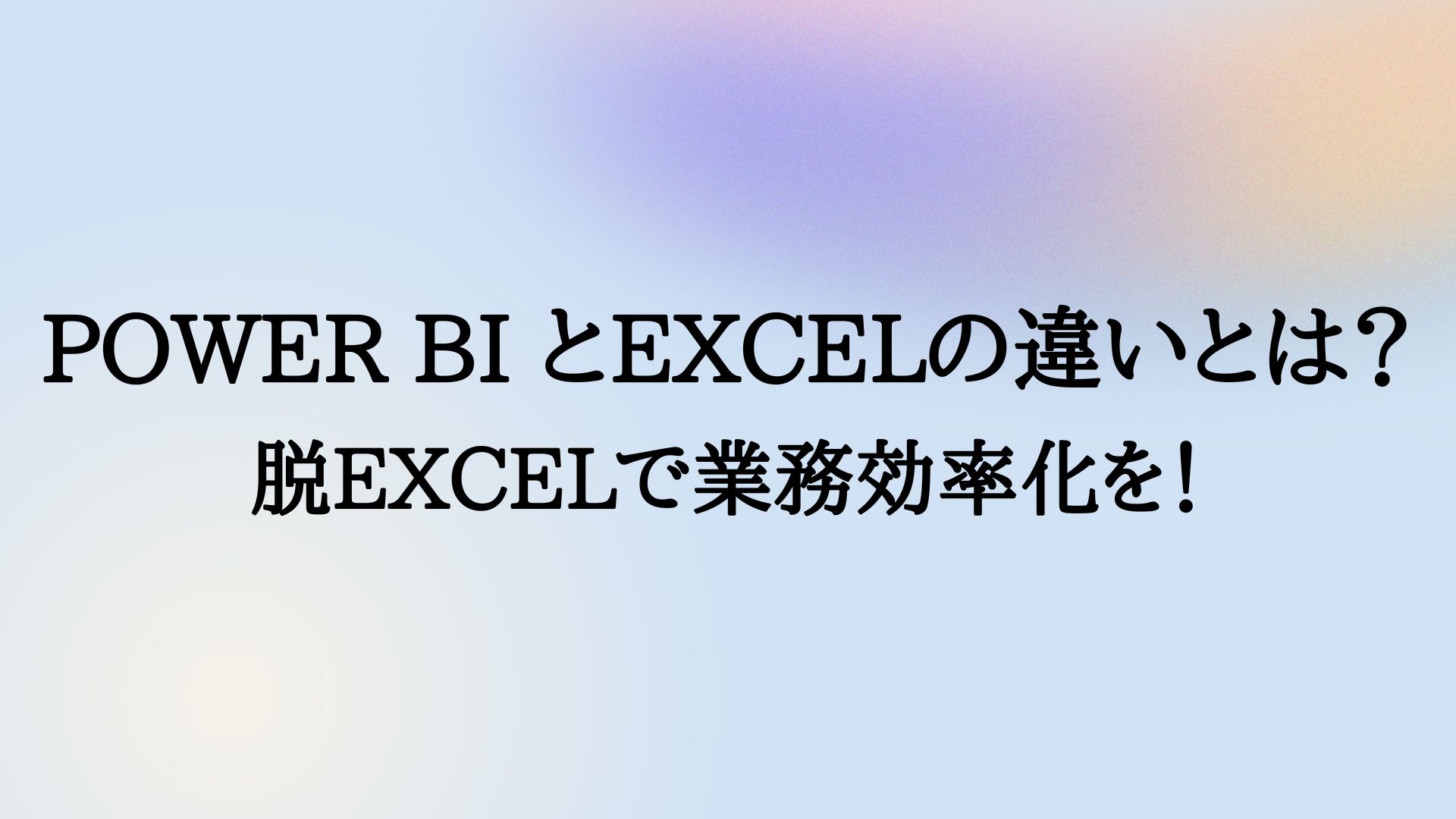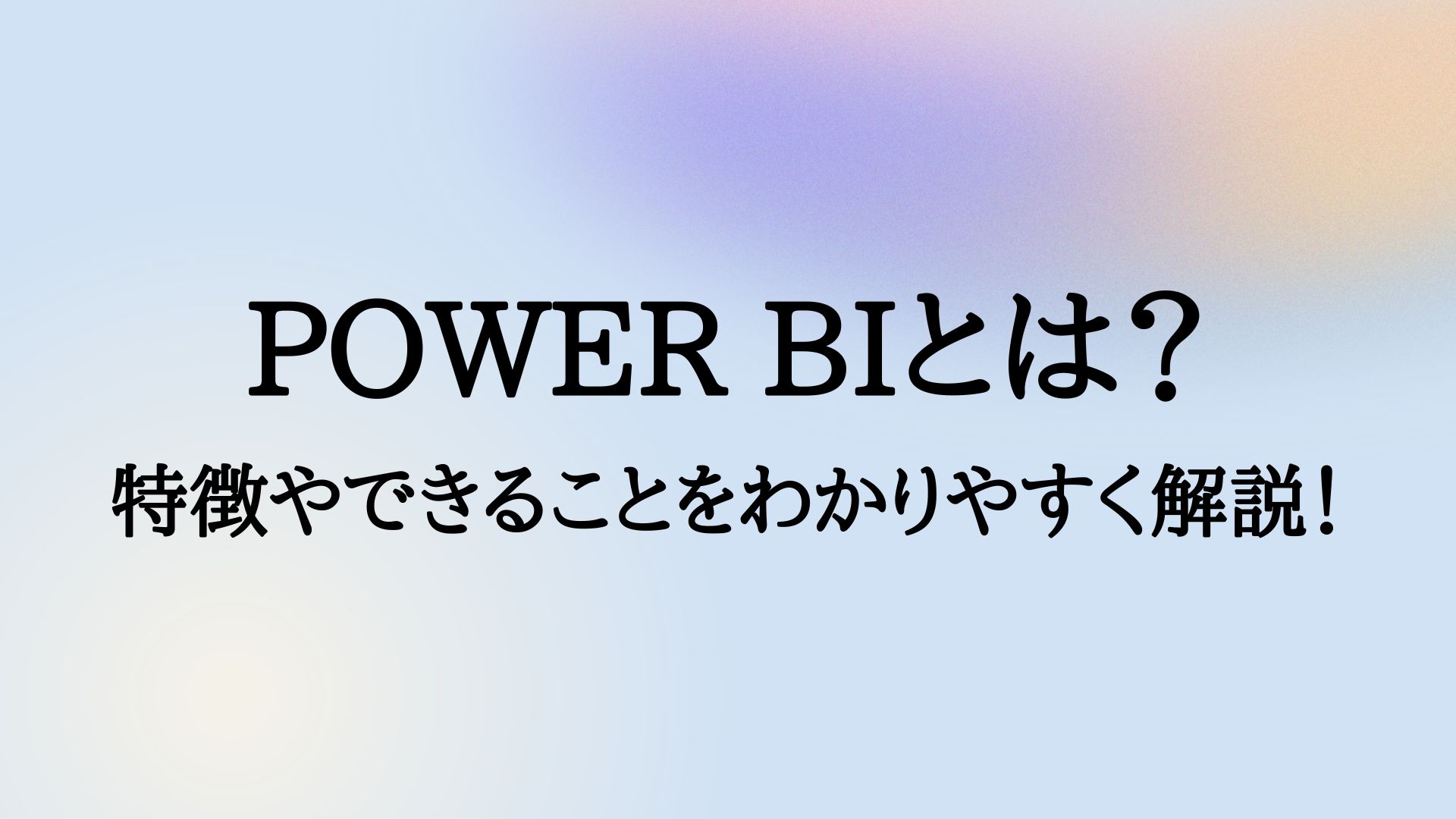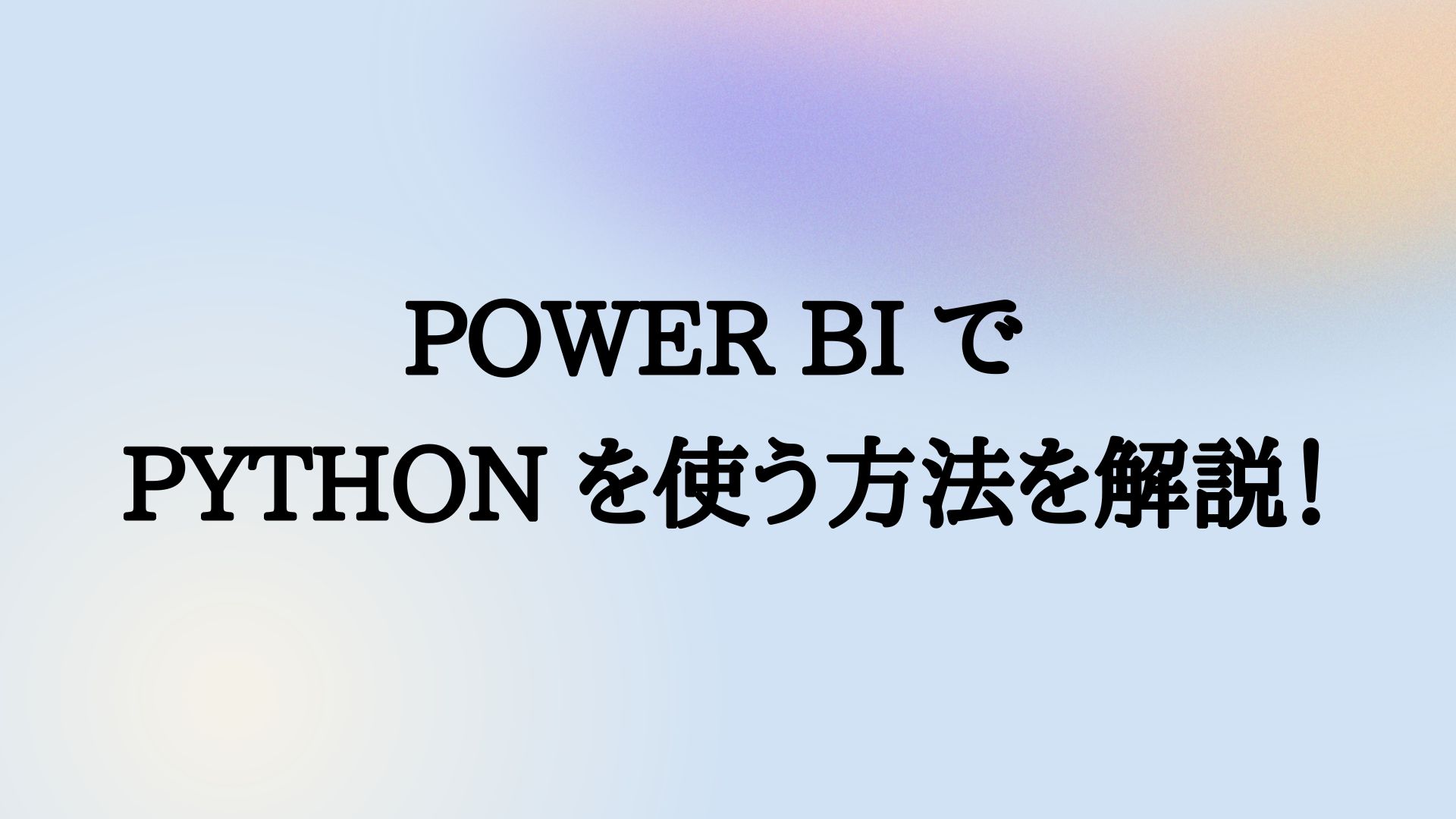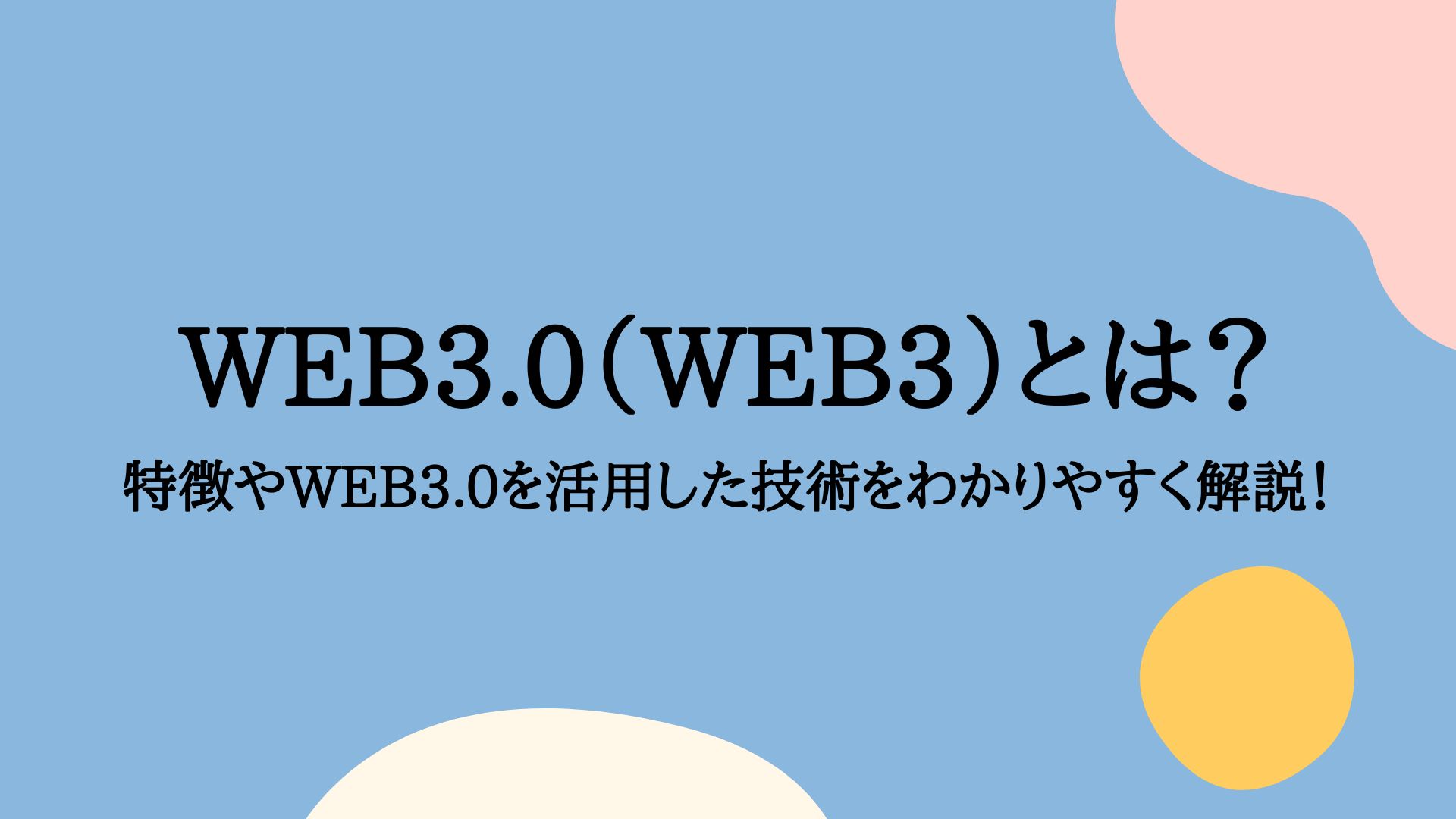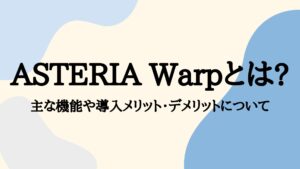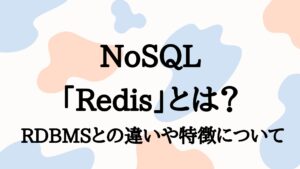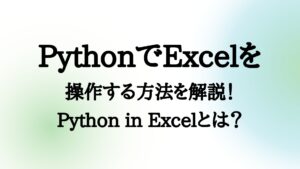「Web3.0」または、「Web3」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。
「聞いたことあるけど、結局なんなの?」
「Web3.0(Web3)になると、どうなるの?どんなことができるようになるの?」
といった方も多いことと思います。
Web3.0(Web3)を一言で表すと、“ブロックチェーン技術により実現された次世代型の分散型インターネット”です。
Web3.0(Web3)を活用したNFTやDAO、メタバースなどは、ECに携わっている方やマーケティング担当者の方などを中心に、今後のマーケティング戦略を考える上で必要となる知識となります。
本記事では、データの可視化・分析、その他データ活用に関する多くの知見のある株式会社KUIXがこれまでの経験をもとにWeb3.0(Web3)の概要や特徴、代表的な技術、注意点をわかりやすく解説いたします。
Web3.0(Web3)とは?
前述の通り、Web3.0(Web3)とは、”ブロックチェーン技術により実現された次世代型の分散型インターネット”です。
何かを調べたり、動画を視聴・配信する際は、GoogleやTwitter、Instagram、YouTubeなどのプラットフォームを利用しますよね?
このようなプラットフォームの管理者が中心に存在している中央集権型のサービスでは、管理者が定めたルール(規約)に違反した場合、アカウントの凍結やサービスを利用できなくなることもあります。
一方で、Web3.0の世界では、ブロックチェーン技術を用いることで、プラットフォームへの権力集中を回避でき、全てのインターネット参加者が自由に表現や取引をすることが可能となります。
具体的には、Web3.0ではすべてのインターネットに参加者のコンピュータを使って情報を管理するため、各コンピューターによって演算処理が分散され、企業や個人に権力が集中する中央集権型のサービスを回避できるようになります。
Web○○とは?
「Web3.0」と同様に、Web1.0、Web2.0もあります。ここでは、Web○○について説明します。
Web○○は、インターネット構造を表す概念です。
インターネットの普及が始まった1990年頃からのインターネットの構造を分類しています。
Web1.0、Web2.0、Web3.0の違い
Web1.0、Web2.0、Web3.0それぞれの時期、特徴、主なサービスなどの違いを説明します。
〇Web1.0
・時期:1990年頃〜2000年初頭頃
・特徴:発信者がごく一部(企業など)に限られていた黎明期のインターネット
・主なサービス:ホームページ、メール
・ユーザの使い方:読む(一方向)
・利用技術:HTML
・構造:静的
〇Web2.0
・時期:2005年頃〜現在
・特徴:誰もが発信者となり双方向のコミュニケーションが可能なインターネット
・主なサービス:SNS
・ユーザの使い方:読む・書く(双方向)
・利用技術:JavaScript
・構造:動的
〇Web3.0
・時期:2018年頃〜現在
・特徴:ブロックチェーン技術を用いた情報の分散化および、改ざんできない安全性、取引の透明性があるインターネット
・主なサービス:DApps
・ユーザの使い方:所有する
・利用技術:ブロックチェーン
・構造:分散型
Web3.0とWeb3の違い
前述のWeb○○とは?で説明しました通り、Web○○は、インターネット構造を表す概念です。
Web3.0をWeb3と記載している記事も多くありますが、Web3は、イーサリアムの共同設立者であるギャビン・ウッド氏が、2014年に「ブロックチェーンに基づく分散型オンライン・エコシステム」と定義した造語であるため、Web3.0とWeb3は異なる概念になります。
Web3.0の特徴
ここからは、主にWeb3.0の特徴を説明します。
Web2.0では、GoogleやTwitter、Instagram、YouTubeなどの大きなプラットフォーマーや企業、組織が個人のデータや権利を管理しています。
そうしたサービスを活用することで私たちの便利な生活が成り立っている一方で、
「情報漏洩が怖い」
「情報を握られていると感じるため、個人情報を登録したくない」
といった不安を持つ方も多くいらっしゃると思います。また、実際にハッキングによって、多くの個人情報が流出する事件も発生しています。
Web3.0によって、個人情報をプラットフォームに預けるのではなく、ブロックチェーンによって分散管理することで、一方的なアカウントの凍結や削除、情報の改ざん、情報公開の停止といったことを回避することが可能になります。そのため、個人情報について、大きなプラットフォーマーや企業、組織に委ねるリスクと、個人が管理することによるメリット・言論の自由が注目されており、Web3.0(分散型インターネット)への関心が高まっています。
ユーザーがデータを所有する
Web2.0では、GoogleやTwitter、Instagram、YouTubeなどの大きなプラットフォーマーや企業、組織が個人のデータや権利を管理しています。
例えば、Amazonや楽天市場などのネットショッピングで購入した商品の履歴は、Amazonや楽天市場などのプラットフォーム側で削除されてしまえば、ユーザは購入履歴を見れなくなってしまいます。
しかしWeb3.0では、そのようなユーザ情報や購入履歴などは、分散管理されるため、ユーザがデータを所有できるようになります。
そのため、一方的なアカウントの凍結や削除、情報の改ざん、情報公開の停止(データ消失)といったことを回避することができるようになります。
セキュリティが向上する
GoogleやTwitter、Instagram、YouTubeなどの大きなプラットフォーマーや企業、組織がサイバー攻撃されるとどうなるでしょう。
ユーザの氏名、住所、クレジットカード情報などの個人情報が流出する可能性がありますよね?
Web3.0では、ブロックチェーン技術により情報を分散して管理しているため、情報漏洩が起こることはありません。
そもそも、Web3.0では、パスワードやメールアドレスなどは登録せずに利用することができるため、セキュリティ面が向上します。
誰でも自由に参加し、自由な表現ができる
Web3.0では、誰でも自由にインターネットに参加して自由な表現ができるようになります。
GoogleやTwitter、Instagram、YouTubeなどの大きなプラットフォーマーや企業、組織などによって、SNSに発信する内容を制限したり情報の検閲がされることもありません。
このように、データを管理するプラットフォーム(仲介組織)を介さず、個人間で自由にコミュニケーションを取れるようになるため、誰でも自由に参加し、自由な表現ができるようになります。
また、仲介組織が不要になるため、仲介組織に支払っていた手数料なども不要となり、真のグローバル市場が確立されるようになります。
今まで同じサービスでも、国や地域によって異なる料金形態となっていたサービスでも、Web3.0では、世界中どこにいても同じサービスが利用可能になります。
Web3.0を活用した代表的な技術
Web3.0の技術は、すでにさまざまな分野で活用・導入されています。
ここでは、Web3.0を活用した代表的な技術を紹介します。
〇NFT
NFTは、「Non Fungible Token」の略称で、翻訳すると「非代替性トークン」です。
オンラインゲームのアイテムやトレーディングカードなどのデジタルデータは、複製や改ざんをされているか判断できませんよね?
しかし、ブロックチェーンの技術を活用することで、デジタルデータであっても複製ではない本物であることを証明することができます。
ブランド品などの実際の商品にもシリアルナンバーを照合することで、世界に100点しかない商品であることを証明することができますが、それのデジタルバージョンとイメージしてもらえればわかりやすいと思います。
なお、ブロックチェーンでは、商品購入など取引データがすべて記録として残ります。そのため、過去に所有していた人が有名アーティストやスポーツ選手だった場合、価値が上がることもあり得ます。
また、取引で発生した利益の〇%をアーティスト(著者)に還元するというルールを設定することもできるため、作品の価値が上がることで、アーティストにも利益が還元される仕組みを作ることもできます。
〇メタバース
メタバースは、Meta:超越とUniverse:宇宙から作られた造語でインターネット上に構築された仮想空間です。
2021年10月Facebook社がMetaへ社名を変更し、メタバース事業に積極的に投資していくとマーク・ザッカーバーグが発表したことで、メタバースという言葉が広く知られるようになりました。
実際に遠くにいたとしても、インターネット上のバーチャル空間でコミュニケーションや、ゲームができるとイメージしてもらえればわかりやすいと思います。
バーチャル空間上の美術館でデジタルアート作品を閲覧したり、アーティストライブに参加したり、アパレルブランドによるショップ展開など、経済圏としても急速に成長しています。
今後、VRゴーグルの軽量化や通信の高速化などの課題が解決されることで、メタバース上で1日のほとんどの時間を過ごし、生計を立てる人も出てくると言われています。
Web3.0が抱える問題点・課題点
ここまでの内容で、Web3.0になると良いことばかりと思うかもしれませんが、Web3.0の場合、データはプラットフォームでは管理していないため、万が一、データ流出などのトラブルが発生した場合は、自らが対応しなければなりません。そのため、セキュリティの高いデータ管理方法や、トラブル発生時の対応方法を把握していないと使いこなすことは難しいことがあります。
また、今後、Web3.0を活用する上で法整備やルールが設けられていくことになると思いますが、安全に利用できるようになる一方で、規制によってWeb3.0本来の恩恵が受けられなく可能性もあります。
利用までのハードルが高い
Web3.0を活用したサービスでは、基本的に仮想通貨を利用することになります。
そのため、仮想通貨などの知識など一定のITリテラシーが求められます。仮想通貨購入までのステップも簡単ではなく、誰でも気軽に利用することは難しいことがあります。
トラブルは自己責任で処理する
Web2.0では、GoogleやTwitter、Instagram、YouTubeなどのサービスは誰でも利用でき、ログインするためにはIDとパスワードを入力し、万が一、忘れてしまっても運営側に問い合わせをすることで再登録や再発行で対処できます。
しかし、Web3.0では、IDやパスワードが不要になりますが、データを個人で管理する必要があり、クレジットカード情報などの決済情報を第三者に盗まれて被害を受けても、救済を求めることができません。
そのため、Web3.0では、データ流出などのトラブルが発生しても個人で対処する必要があり、セキュリティの高いデータ管理方法や、トラブル発生時の対応方法を把握していないと使いこなすことは難しいことがあります。
法的に整備されていない
2023年時点で、web3.0に必要な法整備はほとんど進んでいないため、一般社会に普及するまでには時間がかかる可能性が高いです。
アメリカのベンチャーキャピタル会社であるアンドリーセン・ホロウィッツは、2022年1月22日にweb3.0が社会に利益をもたらすための10原則を発表しました。
この10原則はWeb3.0を普及させる各国政府が実行すべき指針をまとめたものですが、規制の調整や監視体制の構築に伴う法整備は間に合っていない状況です。
まとめ
Web3.0は、今後、ますます注目の高まることが予想されますが、技術的/法制度/リテラシー的課題など多くのハードルがあります。
Web3.0へのシフトが進めば、みなさまの企業がどのように新時代のインターネットに対応し、どのように消費者と向き合うべきなのか?も注目すべきポイントとなります。
そのため、みなさまの企業でのビジネスに活用するためにも、Web3.0について知見を深めることをおすすめいたします。
株式会社KUIXではシステムをただ導入・開発するだけでなく、導入後の利活用を実現することに着眼した、データレイク・DWH・データマート、BIツールの選定・導入からレポート作成、運用、啓蒙・展開までトータルでのサポートを行っています。
「データマート/データレイク/DWH/BIツールを導入したい」
「データ活用、展開が進んでいない」など
お困りの方は、ぜひお気軽にご連絡ください!お問い合わせはこちらから